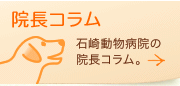口腔衛生の重要性 [院長ブログ]
●歯周疾患は、全身性合併症(心臓、肺、腎臓病変)を起こすことがある侮れない病気です。歯石が蓄積するとそこに大量の細菌が繁殖します。その細菌が血液に乗って全身の組織へ運ばれ、心内膜炎、腎盂腎炎、慢性気管支炎などの原因になります。
●慢性気管支炎
犬の慢性気管支炎は、末端の気管分枝の平滑筋が肥厚して肺胞の空気が出せなくなる状態を言います。慢性となると完治はできず、生活の質を向上させる治療になります。
この原因の一つに、歯周病が関連していると言われています。口腔内の細菌が、血行に乗り肺へ、また、口腔内から直接肺へ感染する経路が考えられます。
●歯石の形成
歯垢が付着し、唾液中のカルシュウムとリンがにより歯石が形成されます。歯石形成により歯肉炎により歯ぐきが後退、歯石が接触する口腔粘膜の潰瘍化が起こります。歯垢には多くの細菌が含まれ、歯肉炎を進行させます。
●歯の管理
上記の状態に進まない様にするには、食事と歯磨きです。当院は、基本的に生食を勧めていますが、40%の方はドライフードと缶を食されています。生にすると生に含まれる酵素の作用で歯石が形成されにくくなりますが、それでも、食後の歯磨きが理想的です。
●口腔衛生の重要性
上記の内容より歯垢による細菌感染、その炎症による歯肉炎、歯肉炎による痛み、歯垢から歯石の蓄積、そして、歯肉縁下に歯石が入り込み歯の脱落と悪いことばかり起こります。できるだけ早い対応が必要です。
●まずは、我が家の動物の口の中を直ぐに覗いて見てください!
関連タグ :
前十字靱帯断裂と膝蓋骨内方脱臼 [院長ブログ]
●ジョン 9歳 ヨークシャテリア
原因不明だが、「帰宅してみると足を着かなくなっていた」との主訴で広島から来院されました。鎮静をかけて検査をすると、前十字靱帯断裂が発見されました。
●十字靱帯断裂
膝を切開している所です。ピンセットの下に小さく見える白い2つの点が断裂した前十字靱帯です。関節周囲に骨の増殖が見られ変形性の関節炎の存在が分ります。その異常増殖した骨をけずりとり、そして、断裂した靱帯組織を切除して洗浄を繰り返しました。
●十字靱帯整復
膝の前方移動を抑制するために、膝の骨に穴を開け、小さな骨の下を通して固定します。この固定により前方への引き出す動きが無くなり安定します。
●膝蓋骨内側脱臼
膝蓋骨とは、膝のお皿のことです。この膝蓋骨が先天的に内側に外れる状態を伴っていましたので、この際一緒に治すことにしました。膝蓋骨を受ける側の大腿骨の溝が浅かったので一旦軟骨を削り取り、溝を形成して再び戻しました。2番目の写真と比較すると、その溝が深くなっているのが分ります。飼い主さんの話によると、頻繁に脱臼して、その際には薬を飲んだら治っていたそうですが、この病気は手術をしなければ治りません。そして、薬を飲まなくとも自然に元の位置にもどるのです。小型犬では、先天的に内側脱臼を起こしているケースは山ほど居ます。しかし、日常生活に支障をきたす場合は多くありません。重症度により手術が必要な場合があります。
●膝蓋骨内方脱臼整復
膝蓋骨靱帯とその付着する脛骨との軸のずれはありませんでした。補強処置として、膝の関節包の外側を重ね縫いして内側へのずれをさらに抑制しました。
●術後
術後7日目ぐらいから徐々に足先を着くようになりました。今回は、膝の内側脱臼も整復しましたので、術後かなり腫れがありました。自宅には他に2匹の仲間が待ち受けていますので、入院を少し長めにしていただきました。安静はさらに続き(8週間)ますが、大型犬ほどの厳重管理にはなりませんが、無理は禁物です。
関連タグ :
腫瘍摘出を急がなければならない理由 [院長ブログ]
●例)乳腺腫瘍
過去に何度か登場した乳腺腫瘍ですが、やはり他の腫瘍同様に高齢で発生が多く、我々の元に来た時には既に大きな塊を形成していることが常です。
卵巣摘出とホルモン誘発性の悪性乳腺腫瘍の関係は、初回発情前では99.5%、1回目92%、2回目74%。それ以降(2.5歳)に対して効果なしと言われています。
つまり、不妊術を行うのであれば2歳半までに。そして、同じ行うのであれば、最初の発情前(約6カ月未満)に受けることが効果的です。
●急ぐ理由
という訳で、肺への転移が見られる前に早期に摘出することが重要なことが分かります。年だからという理由で、いつまでも放置して最終的に大きくしてしまい、また、腫瘍が裂けてしまっ慌てふためいて駆け込むケースが多くあります。悪性腫瘍を大きくしてしまうと転移率が高まります。最終的に摘出するのであれば、安全な早い時期に切除することを心がけなければなりません。飼い主さんの決断が、大きく将来を左右します。
●レントゲン検査
乳腺腫瘍に限らず、腫瘍を摘出する場合には、通常胸部のレントゲン撮影を行います。もし、レントゲン写真で転移像があれば、ほとんどのケースで手術を行いません。なぜならば、余命は数カ月です。残念ながら痛い思いをして腫瘍を摘出しても未来を望めないからです。
●早く見つけて素早く切除
若い時期に比べて高齢の手術では、当然リスクが高まります。肝臓障害、腎障害、心不全などが問題になりますが、術前の検査をしっかり受け、肝臓、腎臓、心臓に負担を軽減する麻酔薬を選択しながら手術をおこなえば、高齢だからと言って恐れる必要はありません。
腫瘍を大きくすればするほど手術時間を要し、危険性が高まります。小さな内に安全を確認して早期手術に臨むことがなによりです。
年だからこそ、腫瘍の発生が増加するのです!
年だからと諦めずに早い時期に対処すべきことを忘れずに!