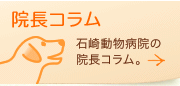�a�C�ɂȂ�Ȃ��������Ƃ� [�悭���鎿��]
������Ȃ��Ƃ́A
�a�C�ɂȂ�Ȃ��������ł��B
�ȉ��̎����������\���ɒ��ӂ��āA�a�C�ɂ����Ȃ��悤�ɏd�X�����ӂ��������B
�����傳��ɂ��\���ʂ�����e�ł��B
�����傳���Ẵy�b�g�ł�����A���l�ɂ����ӂ��������B
���̉��ቺ��h��������
�F���Ȃ��݂̐��I�����H���ɉ����邱�Ƃ������߂��Ă��܂��B
�i�L�����ɂ́A�������Ǝv���܂��B�j
���́A���I�͊������50���̃x�[�X�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B
�̉����㏸����ƁA���s���悭�Ȃ�A�����p���̐��������A�Ɖu�͂��㏸���܂��B
���X�g���X��^���Ȃ�������
�X�g���X��������ƁA�����_�o���D�ʂɂȂ�A���ǂ����܂�A�̉���������A�����p�����ቺ���A�Ɖu���ቺ���܂��B
�u�a�C�̎��ɂ́A�����傳��̒g�����D�����蓖�āv���K�v�ɂȂ�܂��B
�܂��A���i�̐����ł��A�D�������t�������āA�J�߂Ĉ�āA�������_�o��D�ʂɂ���悤�S�|���Ă��������B
�����S�ŁA��`�q�ɉ������H����H�ׂ遚����
�����������L����������c�l�́A���H�b�ł��B
��`�q�̎w�߂ɏ]���āA���S�A���S�ȐH�ו���^���邱�Ƃ��A�ŏd�v�����ł��I
�����������z�킹�Ȃ�
���͑����֗���܂�����A�l�Ԉȏ�ɉ����z�����ƂɂȂ�܂��B�^�o�R���l�オ�肷�邱�Ƃł�����A������@��ɁA�����傳��ׂ̈ɂ��։����܂��傤�I
���d���g����g�����
��Ɍ����Ȃ��d�q�g�́A�̂̃o�����X������܂��B
�ł��邩����A�d���g�ɐG��Ȃ�������S�����܂��傤�I
�d�q�����W�Łu�`���B�v���ė^���Ă͂����܂���B
�����S�ȁu���v��^����
�̂̂V�O���͐����ł��B
���S�A���S�Ȃ����������������Ƃ́A�H���Ɠ������ƂĂ���Ȃ��Ƃł��B
�����̎������������� [�悭���鎿��]
�ے�Ƃ́A������ێ����邱�Ƃ������܂��B�ے莟��œ����̐g�̂ւ̕��S���y������܂��̂ŁA������i�Ǘ��ҁj�Ƃ��Đ������ے�������Ă��������B �����A���ːڎ��̌����̂ݕے���s���܂��ƁA�����ɂƂ��Č��ȋL�����c���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��̂ŁA���i���牺�L�̕ے�����݂�悤�ɂ��Ă��������B �����āA��肭�ł����i�����Ƃ��Ă����j���ɂ́A�����ɂ��J���������邩�A��������ƖJ�߂Ă����Ă��������B��������ƁA�ǂ��L���Ƃ��ăC���v�b�g����A�X���[�Y�ɕے肪�s����悤�ɂȂ�܂��B
���^���ɂ�����ے�@
1. �Иr���A�̉�����ʂ��A����x������B
2. ���Ɏc��Иr��w�����炨���ɂ܂킷�B
3. ���r���y�������̋��Ɉ����悹��B
�����E�ŗ��K���Ă��������I
��^���ɂ�����ے�@
1. �Иr���A�̉�����ʂ��A����x������B
2. �c��Иr�����̉�����ʂ��A�w������B
3. ���r���������A���𖧒�������B
4. �㕔�̎҂Ƒ������킹�āA�����グ��B
��1 ���E�ŗ��K���Ă��������I
��2 ���傳��́A�������������点�āA�O���������K�����Ă��������B�㕔�́A�X�^�b�t�������グ�܂��B
���N�`���i�R�̌����j [�f�@�E��p�̈ē�]
������w�̍l���ł́A���N�`���͂�����u�דŁv�ɂ�����܂��B�u�����ēł�̂ɒ�������K�v������̂��H�v�u�l�Ԃł́A���N���N�`���ڎ�����Ă��Ȃ��̂ɂ��̕K�v������̂��H�v�u�A�����J�̈ꕔ�ł́A���N�`���͂R�N�Ɉ��ڎ�Ȃ̂ɖ��N�̕K�v������́H�v�Ȃǂ̋^�₪�N���܂����B
�����ŁA���N�`�����[�J�[�̃T�|�[�g���Ȃ��瓖�@�Œ������d�˂����ʁA�E�C���X�̎�ނɂ�葽���̍�������܂����A��U�T���̓��������N�̃��N�`���ڎ킪�K�v�������Ƃ�������܂����B
����A���N�ڎ킵�Ă���̂ɂ��ւ�炸�A���N�ɂ͍R�̉�����l���ቺ���A���N�̃��N�`���ڎ킪�K�v�ȓ��������܂����B
�����܂ł������傳��ɑI��Ղ��܂����A�܂��͍R�̌������s���A���̌��ʂɊ�Â����u�̂ɕ��ׂ̂�����Ȃ��D�����ڎ�v�������߂��Ă��܂��B
��j���̃��N�`���ڎ�̗���
�@�E�C���X�̎��
�@�@���W�X�e���p�[
�@�A���p���{
�@�B���A�f�m
�@�@�̌��ˁ@��V���ԑҋ@�@�ˍR�̉�����l�Ɠ���or�Ⴂ�ꍇ�Ƀ��N�`���ڎ�
��j�L�̃��N�`���ڎ�̗���
�@�E�C���X�̎��
�@�@�L�`��������
�@�A�L�w���y�X
�@�B�L�J���V
�@�@�̌��˖�7���ԑҋ@�ˍR�̉�����l�Ɠ���or�Ⴂ�ꍇ�ɂ̓��N�`���ڎ�
���R�̌�������
���@�ł́A�R�N�Ԃɓn��A���N�A����U�O�O���A�L��P�Q�O���̍R�̌������s���܂����B���̌������n�߂����������́A�u�l�ł́A���N���N�`���ڎ�����Ă��Ȃ��I�v�܂��u�A�����J�̏B�ɂ���ẮA�R�N�ɂP��ڎ�ł���B�v�����āu�A�����J�̎��R�h�b��t�c�̂́A���N�`�����˂��Ƃŕa�C�̔������܂˂��̂Ŏ˂ׂ��łȂ��I�Ƃ܂ői���Ă���v�Ȃǂ̋^�₩��ł����B
�ȉ��������������ڂƌ��ʂł��B
���������e
���̓W�X�e���p�[�A�p���{�E�C���X
�L�̓w���y�X�A�J���V�A�L�`���������E�C���X
��L���ꂼ��ŁA�R�̕s�������݂����ꍇ��ڎ�K�v�Ƃ��܂����B
�������P�W�N�́A���ł́A���N�`���ڎ킪�U�T���ŕs�v�ł����B
�L�ł́A�V�P���ŕs�v�ł����B
�������P�X�N�́A���ł́A�������U�T���B�L�ł́A�V�P�������N�`���s�v�ł����B
�������Q�O�N�A���ł́A����ɓ������U�T���ŕs�v�B
�L�ł͂T�W���s�v�ł����B
�����_
���A�L���ɁA�����悻�U���Ń��N�`���ڎ킪�s�v�ł����B
������̒��ɂ́A�R�N�Ԑڎ�s�v�̃P�[�X������A���N�̉ߏ�ڎ������邽�߂ɂ��A�R�̌����m�F��A���N�`���̍Đڎ���������邱�Ƃ��A�̂ɗD�����ǂ����@���ƕ�����܂����B
�܂�u�U���ȏ�ŁA���N�`���́A���N�˂K�v���Ȃ��I�v�������u�̍�������̂ŁA�X�ɍR�̌����Œ��ׂ�K�v������I�v�ƌ��_�Â����܂���
���@�ɂ��ċ����� [�悭���鎿��]
���@�Ɋւ��Ă��������܂��B
���@����
�e��\�h���N�`�����P�N�ȓ��ɐڎ킵�Ă��Ȃ��ꍇ�A���邢�́A�R�̉����K��l�ɒB���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�lj��ڎ킠�邢�̓C���^�[�t�F������ڎ킳���Ă��������܂��B
�܂��A�m�~�Ȃǂ���������A�쒎���u������Ă��Ȃ������́A���̍ۂɏ��u�������Ă��������܂��B
���@���ɑ��̕a�C�̔����A�܂��͔������ꂽ�ꍇ�ɂ́A���ÁA��p�A���̑��̏��u���s�����Ƃ��������Ă��������A�����������Ă��������܂��B
���ّ̎��ɂ��s���̎��́A�V�ЂȂǂ̎~�ނ��錴���ɂ�鎸�H�A���S�A�����̏ꍇ�ɂ́A�����A���Q�⏞���̐����͂��ł��܂���̂ł��������������B
���@���A�[��Ɏc�O�Ȃ���S���Ȃ����ꍇ�ɂ́A�����ɂȂ�܂ł��A���ł��܂���̂ł��������������B
�Ђǂ��i����A���Âɂł��Ȃ��ȂǓ��@�Ǘ�������ȏꍇ�ɂ́A���Í܂𓊗^�������Ă��������܂��B
�܂��A���^���s�\�ȏꍇ�ɂ́A�c�O�Ȃ���މ@���Ă����������Ƃ�����܂��B�����āA�މ@�̎w�����������ꍇ�ɂ͒����Ɉ�������Ă����������Ƃ����������������B
���@����
�T�Z�\�[���S�z�A�܂��͔��z������Ƃ��Ă��a���肳���Ă��������܂��B�����āA�މ@���ɐ��Z�����Ă��������܂��B���̍ۂɈ�ӁE�؈�����������������B
���@���̘A���Ɩʉ�
��p�̏ꍇ�ɂ͓����ɒS���ォ��A��������܂��B����ȍ~�́A���@���Ԃ��疈���̂��l�q�����A�����܂��B�ʉ�͗\�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁA���炩���߂��d�b�܂��͎t���ł��\�������B�܂��A�����ɂ���Ă͖ʉ�ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ł��������������B
���a����i
��������A�^�I�����������Q�����ꍇ�ɂ͖ŋۂ̊W��A���̖ŋە��ƈꏏ�ɂȂ蕴������ꍇ������܂��̂ŗ\�߂��������������B�Ȃ��A���a���肵���i���������ꍇ�̔��������͂��ł��܂���̂ŁA���������������B
�މ@
�މ@�����ɍŏI��v�����肢�������܂��B�������@�̏ꍇ�ɂ́A1�T�Ԃ��Ƃɓ������邢�͑S�z���x���������肢���܂��B�����A��̍ۂ͓��@������������܂���B
�e�팟�� [�f�@�E��p�̈ē�]
������N����
�\�h����Ԃł����A���ɑ�Ȃ��Ƃ́A�����f�f�ł��ˁB
���������l�R�����̔N��́A�l�Ԃ�2��20�ɂ�����A����ȍ~4���N���d�˂܂��B
�l�Ԃ�1�N�Ɉ��̒�����f�́A������3�����Ɉ��Ɠ����ƂȂ�܂��B����āA7�͐l�Ԃ�40�ɑ������܂��B�܂�A�V�Έȍ~�́u���N��v�ɓ���܂��̂ŁA���Ɍ��N�f�f�̉�K�v�Ƃ���܂��B
�@��������f�v���O�����P��7�܂Ł@�N�P��i���z��2��j
�@��������f�v���O�����Q��7�Έȍ~�@�N�Q��i���z��4��j
�@��������f�v���u�������e��
�@�@�@�S�g�g�̌���
�@�@�A�o�C�I���]�i���X����
�@�@�B���������g�Q�������i���������g�j
�@�@�C�A����
�@�@�D���������g����
�@�@�E�S�g���t����
�o�C�I���]�i���X����
���̋��̎d�g�݂ɂ����g������������Ȃ��܂��B
���a�A�a�C�̏�Ԃ��זE���x���ő��肵�܂��B
�u�o�C�I���]�i���X�v�̃y�[�W���Q�Ƃ��������B
![]()
�����g�����́A��ɐS���ƕ����A�\�w�̓�g�D�̌����Ƒg�D�̎�ɗp���܂��B�����g�Q�������ł͐S���̌`��傫������������܂��A�����g�����ł͐S���̕ق̌`�ԁA�����̋t���A�S���̎��k�̋����A�t�����t�̑��x�A�e�ʑ���ȂǂɎg���܂��B
�����̌����ł́A�����g�Q���ł͔��f���ɂ����e����̓����\���A����̑傫���A��ᎁA���A�����p�߁A���ǁA��D�w�َ��f�f�ȂǂɎg���܂��B
�\�w�����ł́A�畆�̉��̎�ᎁA�b��B�Ȃǂ̌����Ɏg���܂��B
�����g�����́A���A�x�Ɋւ��Ă͐f�f���ł��܂���B�܂��A�݁A���ɃK�X�����܂��Ă���ꍇ�ɂ́A���̉��̑���͐f�f���ɂ����Ȃ�܂��B����āA�������́A��H���Ă��������܂��B
�����������g�����ɂ��Ă̏ڍׂ����������������������B
�����������g�����ɂ��Ă̏ڍׂ����������������������B
�������g�����\�����݈ē���
�ʏ�A�����ɂ͒ɂ݂����Ƃ��Ȃ����߁A�����������܂��A�������ꍇ�ɂ͒��Ï��u�������Ă����������Ƃ�����܂��̂ŁA�����̐�H�A�����Ă��\��̏エ���ʼn������B���������g�����ł́A�݂ɐH�ו�������ƔS���ʂ��ώ@���ɂ����Ȃ�܂��̂ŁA�O���̖�9���ȍ~�͕K����H���Ă��������B
![]()
�A�����́A���t�������y���v��ꂪ���ł����A�����̏��������点�Ă���܂��B���Ԃ��o�߂��Ă��܂��ƔA���ω����������Ă��܂��܂��̂ŁA�̎��ɁA�ł��邾�����₩�Ɍ������Ȃ���Ȃ�܂���B
���̔A�����ŁA�ُ�������ꍇ�ɂ́A�N���ɒ��ڐj���h���č̔A���s���A�Č����i�݂܂��B
�L�̖����t�s�S�����t������葁���ɔ������邽�߂ɁA�A���`���A�N���A�`�j����̑�������I�ɍs�����Ƃ���ł��B
![]()
�g�̌����A�A�������ƂĂ���ł����A���t��������������̏��邱�Ƃ��ł��܂��B�n���A�h�{��ԁA�̑��A�t���A���t�Ȃǂ̏�Ԃ��܂��ɔc���ł��܂��B����̕a�C���^���A���̓��ꌟ���i�݂܂��B
![]()
���ɎႢ�����ł́A���̐S�z������܂��̂ŁA�Ǖւł����Ă��A�������������߂��Ă��܂��B
1�Έȍ~�́A�N�ɂP����x�̌��������Ă��������B
�܂��A���C�������āA�}�������ŕa�@�ɘA��Ă���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�܂��A��H�����āA�H���Ö@�̎w������f�������B